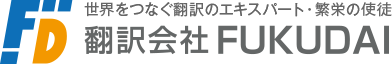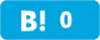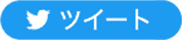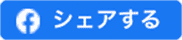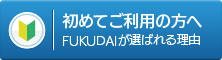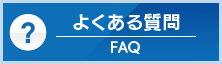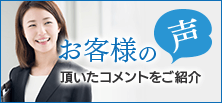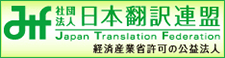翻訳コラム
2021.02.10
翻訳物の著作権所有者は誰?トラブル回避のポイントやAI翻訳の著作権についても解説

多くの企業が海外進出を遂げるなど日本が海外と密接な関係にある今、企業間の取引の際に契約書やマニュアルの翻訳が必要となり、翻訳会社に依頼する事もあるでしょう。しかし、契約書やマニュアルを翻訳した場合、元の原稿の著作権とは別に、翻訳した原稿の著作権は一体誰のものになるのでしょうか?
そこで本記事では、翻訳物についての著作権問題や翻訳依頼のトラブルを防ぐための注意点についてご紹介したいと思います。また、近年シェアが増しているAI翻訳の著作権の所在についても解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
Index
翻訳物の著作権は誰のもの?二次的著作権について

自分で作成した物語や音楽の歌詞、論文などは著作物と呼ばれており、これらを生み出した作者が著作者と呼ばれます。著作物には言葉の使用未使用関係はなく、創造されたものであれば、作成された時点で著作権が発生します。
著作権所有者以外の無断利用を禁じるとして法律に守られており、もしこの著作物を利用する場合は基本的に所有者の許可や費用の支払いが必要です。
ですが、英語で書かれた書籍を日本語訳にした場合、英語の原文の著作権は書籍の著者ではありますが、日本語訳の著作権は一体誰のものになるのでしょうか?
実はこのような場合、日本語訳された翻訳物には二次的著作権というものが与えられます。二次的著作権は、とある著作物をもとにして翻訳や翻案して創作された著作物に対して与えられる権利であり、先ほどの例に当てはめると日本語訳をした人に与えられる権利になります。
しかしこの二次的著作権は日本語訳をした人だけのものではなく、原著作者もその翻訳や翻案して創作された著作物の著作権を保持しています。そのため、翻訳物の著作権は原著作者と翻訳をした人の両方が所持するものとなるため、訳文の利用やアレンジをする際には原著作者の許可も必要となります。
翻訳会社に依頼した際の著作権は?

先ほどは個人で翻訳をする場合についてご紹介しましたが、翻訳を受け持つ会社である翻訳会社に依頼をした場合はどうなるのでしょうか。結論を申し上げますと、一般的には個人間の翻訳と同じような仕組みになっています。
依頼をした原著作者が自分であれば著作権は自分にあり、二次的著作権は翻訳会社と原著作者にあるとされます。しかし、翻訳解釈によってはこの二次的著作権について宣言している場合も多く、会社によってこの二次的著作権を放棄する・放棄しないといった明言をしていることもあります。
そのため基本的には著作権は原著作者が所有し、二次的著作権は翻訳会社と原著作者が所有ということになりますが、会社によって二次的著作権を放棄する場合もあるため、必ずしも両者が著作権を持っているという状況になるとは言えません。
そのため、翻訳依頼をする前にあらかじめ、翻訳文の取り扱いについて確認をしておくと良いでしょう。
AI翻訳の著作権は?
結論から言うと、AI翻訳は著作権の侵害にはなりえません。これは、日本の著作権法においてAI翻訳による著作物の利用行為は、原則著作権者の承諾を得なくても可能であると規定されているためです。(著作権法30 条の4 第2 号)
しかし、この規定では、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではない」としており、著作権者が法的な手段を実行した場合に、無断で翻訳した内容を掲載していると大きなトラブルとなる可能性があります。
実際に、映画のセリフを翻訳してサイトにアップした男性が、無断転載で逮捕された事例も存在するため、営利目的のAI翻訳の活用には、著作権者の許可を得る必要があるでしょう。
翻訳物の著作権にまつわるよくあるトラブル
二次的著作権について十分に理解していないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
例えば、書籍の翻訳文を翻訳者の許可なく複製した場合、著作権の侵害に該当し、法的措置を取られることもあり得ます。
よくある誤解として、原作者の著作権が没後70年で消滅すると、それに伴い翻訳も自由に利用できると考えてしまうケースがあります。しかし、翻訳者にも著作権が付与されており、その保護期間が残っている場合、無断で使用すれば著作権侵害となってしまいます。
また、海外のウェブサイトに掲載されている有益な情報を、許可なく日本語に翻訳し、自社サイトに掲載した結果、実際に逮捕された事例も報告されています。こうしたリスクを回避するためにも、事前に著作権の要件を整理し、適切な対応を心がけることが重要です。
翻訳依頼による著作権トラブルを防ぐためには?
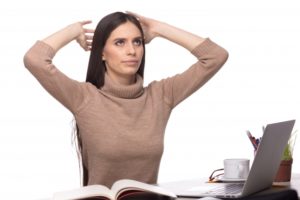
翻訳依頼をした場合、原著作者にも著作権が認められるとお伝えいたしましたが、必ずしもトラブルが起きないというわけではありません。思いがけないトラブルを防ぐためにも、トラブルを回避する方法を知っておきましょう。
どちらに著作権が帰属するのかを明確に記載する
翻訳を依頼する際には、著作権の所在について必ず自演確認を行いましょう。具体的には、書類にて「翻訳物の著作権は依頼者が所有するものである」といったような記載をし、合意を得ましょう。
細かなルールを規定した契約書を作成する
問い合わせや見積もりの際に著作権について確認したとしても、そのまま依頼を進めるのは避けたほうがよいでしょう。
翻訳に関する取り決めや、ローカライズに伴う細かな調整など、具体的なルールを契約書などの書面に明記しておくことが大切です。
信頼できる翻訳会社に依頼する
身近な人に気軽に依頼し、そのままサイトに掲載するのは避けるべきでしょう。たとえその人に翻訳のスキルがあったとしても、著作権などの細かいルールを正しく理解しているとは限りません。
翻訳会社に依頼すると、知人に頼むよりも費用がかかるかもしれませんが、法的なリスクの回避や正確性の面で安心して任せることができます。また、依頼する翻訳会社を選ぶ際は翻訳物の著作権を放棄する事を掲げている会社を選ぶのも一つの方法です。
まとめ

ここまで、翻訳を依頼した際の著作権の所在や翻訳依頼におけるトラブルの回避例をご紹介してきました。他者の著作物を翻訳し個人で楽しむ分には何も問題ありませんが、著作者の許可を得ずにその翻訳原稿を自分発信で公開するとなると、法に反してしまいます。
また、翻訳会社に依頼をする際も、その会社が著作権についてどのような明記をしているのかしっかりと把握しておかなければなりません。
予想外のトラブルに巻き込まれないためにもぜひこの記事を参考に、翻訳会社への依頼を考えてみてはいかがでしょうか。翻訳会社FUKUDAIは、各翻訳分野において豊富な実績を誇る、依頼主様とトラブルが発生しないように細心の注意を払いながら、対応させていただいております。信頼のできる翻訳会社をお探しであれば、ぜひ翻訳会社FUKUDAIへお問い合わせください。
関連記事
スポーツ分野の翻訳業務とは?翻訳のポイントを解説
貿易関係書類の翻訳について詳しく説明
翻訳プロが語る化粧品翻訳:翻訳のコツとポイントとは?
特許翻訳は難しい?翻訳を依頼する前に知っておきたいポイント3つ!
独学での翻訳は危険?自分で翻訳する場合のデメリットや注意点をご紹介
ファッション翻訳の特徴とは?高品質な翻訳を依頼するポイント3つ
翻訳サービスのセキュリティは大丈夫?無料翻訳サイトを使う前に必ずチェック!
海外との取引に欠かせない事業報告書翻訳とは?翻訳する際の4ポイントを解説